2022.06.16



〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2926
診療時間
月・火・水・金9:00〜13:00/14:30〜18:00
土9:00〜15:00


〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2926
診療時間
月・火・水・金9:00〜13:00/14:30〜18:00
土9:00〜15:00
初めての方はこちら
※当院は保険診療から高度な治療まで対応しています
診療案内

インプラント
経験豊富な歯科医師チームが
オーダーメイドなインプラント治療をご提供
インプラント治療は、歯を失ってしまった場合に行う治療で、見た目や機能性が天然の歯とほとんど変わりません。
インプラント専門サイト
オールオンフォー
制限の無い楽しい食事が
たった1日のオールオンフォーで実現
最小4本で全ての歯を支えるインプラント治療です。総入れ歯が合わない、痛みを感じるなどといったお悩みを感じている方におすすめです。
オールオンフォー専門サイト
入れ歯
入れ歯専門医による
精密でお口にフィットする入れ歯作製
院内に常駐している歯科技工士がカウンセリングから治療まで行いますので、患者様の口腔内に合う理想の入れ歯を手に入れることができます。
入れ歯専門サイト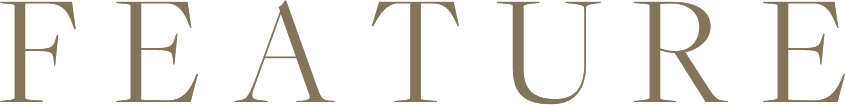
若島歯科医院の特徴


01
分かりやすい
丁寧な説明
治療内容をご理解いただくことが安心に繋がると考えておりますので、分かりやすい丁寧な説明を心がけています。


02
新しい
歯科技術の研鑽
患者様により高品質で低価格な治療をご提供できるように、常に新しい技術を取り入れるようにしています。


03
徹底した
衛生管理
安心して治療を受けていただけるよう、治療に使用した器具の滅菌処理など衛生管理を徹底しています。


04
精密な
検査・診断
3Dによる画像診断ができる歯科用CTによる撮影など、精密な検査・診断後に治療を行うようにしています。


05
痛みに配慮した
治療
患者様になるべく痛みを感じさせないよう表面麻酔の使用など痛みに配慮した治療を行っています。


06
包括的な
治療
一つの症状を診るのではなく、お口の中全体の状態を総合的に考えた包括的な治療を行っています。
PICK UP
短期間でキレイな歯並び白い歯に
ダイヤモンドプレミアムセラミック
6本セット
20%
OFF
660,000円
528,000円
ダイヤモンドプレミアムセラミックとは、
他の素材に比べ、
審美性、機能性、耐久性
など全ての面で優れた審美補綴素材です。
前歯を短期間で美しく
ラミネートベニア
88,000円
院長 若島 満
ご挨拶
チーム医療による
患者様に寄り添った治療で
お口と全身の健康を
サポートします
院長の若島 満です。
当院の治療コンセプトを突き詰めていったときに、いきついたのがチーム医療の導入です。
「チーム医療」とは外科や補綴、矯正歯科治療などを分業して治療を行う方法で、アメリカでは専門制度として発達しているものです。これからも、お一人おひとりのオーダーに応えるために、最善の体制・方針で臨んで参ります。
1人のドクターの治療には限界があります。若島歯科医院では、高度な治療を提供するために、各専門分野(インプラント・入れ歯・矯正歯科・小児歯科・口腔外科・親知らず等)のスタッフとの連携を図っています。
また、歯科衛生士に関しても予防処置のプロフェッショナルとして、一人ひとりが高い技術を有しております。

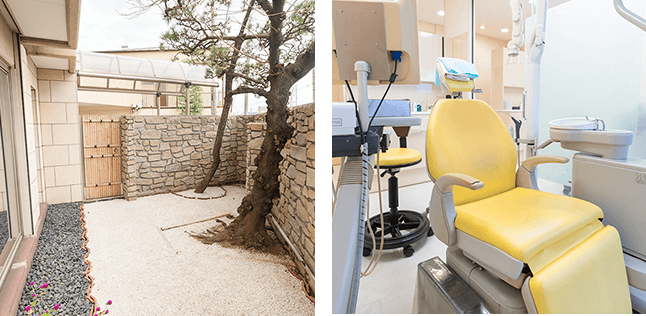
「さいたま市南区・南浦和の歯医者なら若島歯科医院だよね!」「こんな丁寧な歯医者初めて!」「歯医者のイメージが変わった!」「もっと歯医者に行きたくなった!」 私たちは、地域の方々にそう思っていただけるような歯医者を目指しています。
地域で愛され続ける歯医者になるため、スタッフ一丸となって取り組んでいます。
IMFORMATION
- 最新情報 -
コラム
more2022.06.16
お知らせ